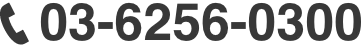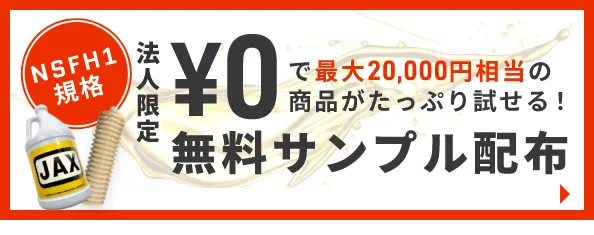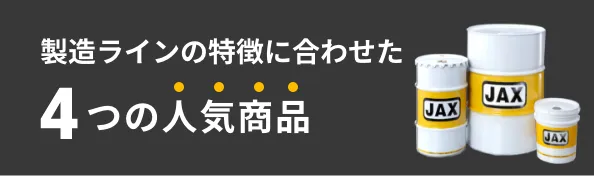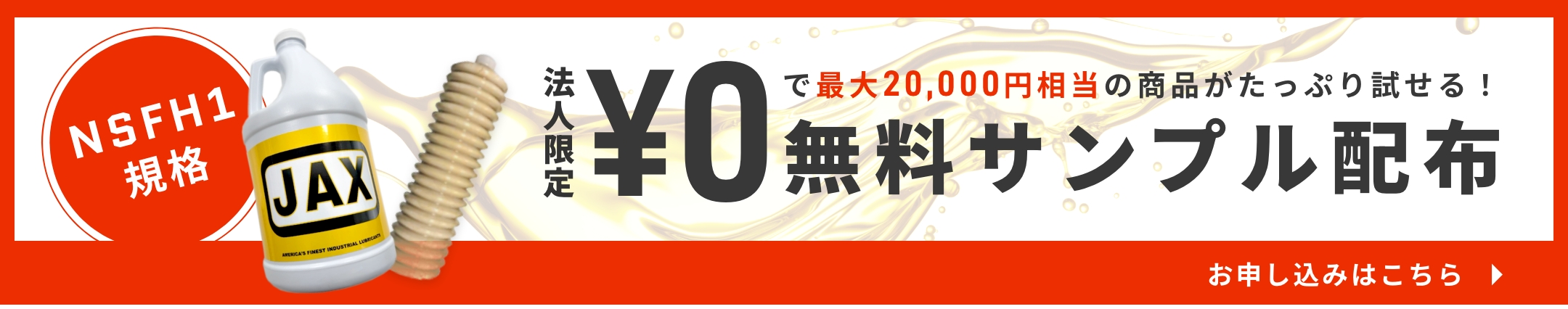潤滑油の油膜とは?自社機械の長寿命化を実現する高性能な製品を紹介
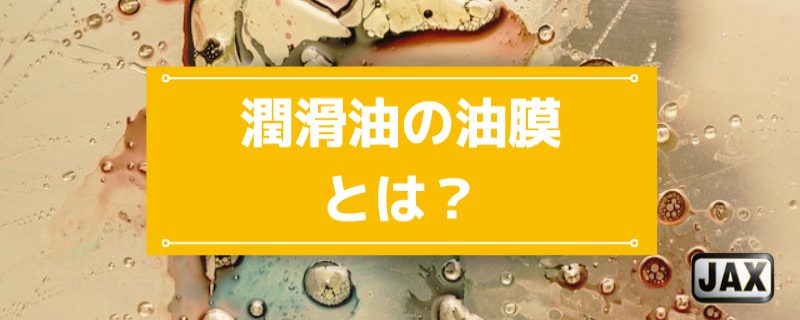
機械潤滑の知識を深めるためには、油膜への正しい理解が必要不可欠です。
要件に合わせて理想的な厚みの油膜を形成することこそが、潤滑の本質であり、自社機械のスムーズな動作を実現するための鍵になります。
この記事では、専門的な知見から潤滑油の油膜を詳しく解説します。
潤滑状態の変化や油膜の厚みを決めるおもな要素、発生するトラブルについて紹介します。
目指すべき最適な潤滑状態を正しく把握するためにも、潤滑の中核的な要素である油膜への理解を深めましょう。
潤滑油の油膜とは

潤滑油の油膜とは、潤滑のプロセスにおいて摩擦面に形成される油の膜のことです。
そもそも潤滑とは、摺動(しゅうどう)する2つの固体間に油膜を形成し、直接的な接触を防ぐことを意味します。
たとえば機械潤滑では、ベアリングやギヤなど摩擦が生じる部品に潤滑油を注油し、油膜を形成することで、摩耗や破損から保護しているのです。
したがって、油膜の形成こそが潤滑油の本質的な機能といえます。
なお、一口に潤滑油といっても用途や性能が異なるさまざまな種類が存在し、製品によって形成する油膜の厚みが異なります。
自社機械の長寿命化や設備メンテナンスのコストダウンを実現するには、油膜や潤滑状態の仕組みを正しく理解し、自社にとって最適な性能を持つ潤滑油を選定する必要があるでしょう。
油膜の厚みによる潤滑状態の変化

油膜の厚みによって潤滑箇所の状態は、以下の3パターンに変化します。
- 境界潤滑状態
- 混合潤滑状態
- 境界潤滑状態
ここからは、各潤滑状態の詳細を解説します。
状態①:境界潤滑状態
境界潤滑状態とは、潤滑箇所の油膜が極めて薄くなり、摺動面同士が接触している状態です。
常に部品同士が摩擦しているわけではありませんが、凸部分を中心に部分的な接触が細かいスパンで発生しています。
なお、境界潤滑状態を一言で表現するのであれば「適切な潤滑ができていない状態」といえます。
機械の動作に伴い、一定のスパンで摺動部品が摩擦し続けているため、摩耗や焼き付きが発生しやすい状況です。
機械故障・破損のリスクが高まるだけでなく、メンテナンスコストも増大しやすい深刻な状況といえるでしょう。
【関連記事】境界潤滑とは?流体潤滑・混合潤滑との違いや発生原因・3つの対策を解説
状態②:流体潤滑状態
流体潤滑状態は、潤滑箇所に必要十分な厚い油膜が形成されており、摺動面同士が直接接触していない状態です。
なお、流体潤滑状態こそが、機械潤滑における理想的な状態を意味します。
動作する機械部品が油膜によって保護され、直接的に接触していないため、摩擦による摩耗・焼き付きを軽減できます。
また、流体潤滑状態は摩擦抵抗が少ない点も特徴です。
したがって、機械のスムーズな動作と長寿命化を実現するには、流体潤滑状態をできるだけ長期間維持する必要があるでしょう。
【関連記事】流体潤滑とは?境界潤滑との違いや適切な潤滑状態をキープする方法を解説
状態③:混合潤滑状態
混合潤滑状態とは、潤滑箇所の油膜が薄くなり、摺動面同士が局所的に接触している状態です。
その名の通り、境界潤滑と流体潤滑が混合している点が、混合潤滑状態の特徴となります。
境界潤滑と比較して、厚い油膜が形成されているため、部品同士の接触は少ないですが、流体潤滑のような理想的な状態とはいえません。
たとえ局所的でも摺動部が接触し、摩擦抵抗が発生するため、摩耗の進行と動力のロスは避けられないでしょう。
潤滑油の油膜の厚さを決めるおもな要素3つ
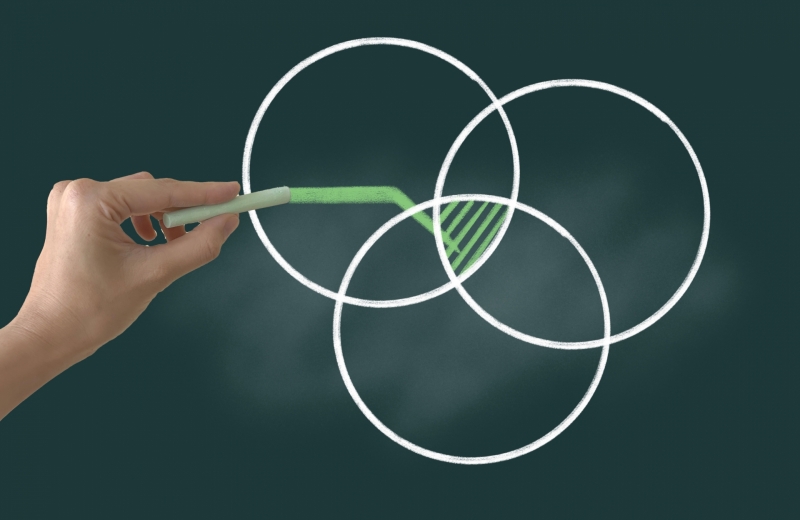
潤滑油における油膜の厚みは、おもに以下の3つの要素で決まります。
- 潤滑油の粘度
- 相対速度
- 荷重
なお、潤滑油の油膜の厚さは「相対速度 × オイル粘度 ÷ 荷重」の式に比例して変化します。
潤滑に関する本質的な理解を深めるためにも、紹介する3つの要素の詳細を確認しておきましょう。
要素①:潤滑油の粘度
潤滑油の油膜の厚さを決める一つめの要素が「粘度」です。
粘度とは、潤滑油の粘り気を示す尺度を意味します。
一般的に粘度が高い潤滑油ほど、厚い油膜を形成するのが特徴です。
前述した通り、油膜の厚さは「相対速度 × オイル粘度 ÷ 荷重」の式に比例して変化します。
上記の式において、相対速度と荷重に定数をあてはめて考えると「潤滑油の粘度が高いほど解が大きくなる=油膜が厚くなる」という結果を導き出せるでしょう。
ただし、相対速度と荷重は機械側の要件であり、基本的に変更・調整するのが困難です。
ベストな潤滑状態を維持するためには、自社の潤滑環境にマッチした適切な粘度の潤滑油を選定する必要があるでしょう。
なお、潤滑油の粘度は、暑さや寒さなどの環境的な要因によって変化します。
特に、場内温度が上がりやすい工場では、オイルの粘度が低下しやすく、結果的に潤滑不良が発生するケースも少なくありません。
そのような高温下における潤滑トラブルへの対策として有効な製品が「耐熱潤滑油」です。
JAX JAPANでは、チェーン油やグリースなど、耐熱性に優れた潤滑剤を各種取り揃えています。
高温下でも優れたパフォーマンスを発揮する高品質な潤滑油をお探しの方は、ぜひ以下の製品ラインナップをご確認ください。
【関連記事】潤滑油の粘度とは?動粘度と粘度指数についても解説
要素②:相対速度
潤滑油の油膜の厚さを決める2つめの要素が「相対速度」です。
相対速度とは、物体1と比較対象となる物体2との間に存在する速度を意味します。
なお、相対速度と油膜の厚みは比例関係にあります。
すなわち、摺動部における相対速度が上昇すればするほど、油膜も厚くなりやすいでしょう。
たとえば、高速で回転するタービンは相対速度が大きく、油膜を形成しやすいため、粘度が低い潤滑油が使用される傾向があります。
要素③:荷重
潤滑油の油膜の厚さを決める最後の要素が「荷重」です。
荷重とは、物体に外部から加わる力や重さ、または構造物の耐久性を示す用語です。
粘度や相対速度とは異なり、油膜の厚さと荷重の大きさは、反比例の関係にあります。
したがって、荷重がかかりやすい潤滑箇所ほど、油膜が薄くなりやすいでしょう。
たとえば、相対速度が低く、高荷重がかかるギヤ部品では、一般的に高粘度の潤滑油が使用されます。
なお、JAX JAPANではギヤ油や油圧作動油、耐圧グリースなど、耐荷重性に優れた各種潤滑剤も提供しております。
自社の環境・用途に最適な潤滑油をお探しの方は、ぜひ以下の製品ラインナップをご確認ください。
潤滑油の油膜が適切に形成されないことで生じる問題4つ

潤滑油の油膜が適切に形成されないと、以下のような問題が発生する可能性があります。
- 摩耗によって機械寿命が短くなる
- 部品の焼き付きやスラッジが発生しやすくなる
- メンテナンスの手間やコストが増える
- 自社製品の品質低下につながる
自社機械を摩擦や劣化から守る対策を講じるためにも、潤滑トラブルの詳細を把握しておきましょう。
問題①:摩耗によって機械寿命が短くなる
潤滑油の油膜が適切に形成されないと、摩耗によって機械寿命が短くなる可能性が高まります。
前述した通り、機械を摩擦・摩耗から守る重要な働きを担っているのが油膜です。
しかし、注油やメンテナンス不足によって、摩擦面が境界潤滑状態に陥ってしまうと、機械部品が直接的に擦れ合う状態で動作し続けることになります。
その結果、機械部品の摩耗が進行し、部品の劣化や破損につながります。
また、摩擦抵抗が高まることで、パーツだけでなく動力を生み出すモーターなどにかかる負担も増大するため、機械全体の寿命を縮める恐れもあるでしょう。
問題②:部品の焼き付きやスラッジが発生しやすくなる
潤滑油の油膜が適切に形成されない状況では、部品の焼き付きやスラッジが発生しやすくなります。
機械部品の焼き付きとは、固体同士の直接接触によって熱が生じ、激しい凝着や溶着が発生する現象です。
一方、スラッジとは、潤滑油の熱劣化や酸化によって生成される炭素の蓄積物のことです。
焼き付きとスラッジは、ともに熱が原因で生じる現象であり、機械のスムーズな動作を妨げる要因となります。
摺動部に適切な油膜が形成されていないと、摩擦によって熱が生じやすくなり、焼き付きとスラッジが発生しやすくなるでしょう。
なお、JAX JAPANではスラッジ問題の解決につながる「浄化作用」を備えた潤滑油を提供しています。
浄化作用の詳細は以下の記事とYouTube動画で解説しているので、ぜひ合わせてご確認ください。
【関連記事】スラッジを除去する3つの方法|発生予防につながる潤滑添加剤も紹介
問題③:メンテナンスの手間やコストが増える
メンテナンスの手間やコストが増える点も企業にとって、大きな問題の一つでしょう。
摩擦面に適切な油膜が形成されていない状態で機械を運転し続けてしまうと、故障や不具合などが発生しやすくなります。
その結果、修理や部品交換などのメンテナンスに時間とコストがかかります。
加えて、再発防止のためにメンテナンスの頻度を増やす必要があるため、コア業務にかけるためのリソースが逼迫してしまうリスクも考えられるでしょう。
問題④:自社製品の品質低下につながる
潤滑箇所に必要十分な油膜が形成されてないと、自社製品の品質低下を招く要因になる可能性があります。
油膜によって十分保護されていない金属部品同士が摩擦されると、お互いを削り合い、金属片が発生します。
細かい粒子となった金属片や不純物が製品に混入することで、品質低下やクレームに発展する恐れがあるでしょう。
特に、異物混入のリスクが高い食品製造工場では、摩耗によって生じる金属片はもちろん、潤滑油自体を製品に付着・混入させないための対策が求められます。
しかし、機械部品の複数箇所に使用されている潤滑油の製品混入を完全に防ぐことは、現実的に困難です。
だからこそ、食品製造工程において、万が一潤滑油が製品に混入してしまい消費者の口に入ったとしても、健康被害を発生させないための対策が必要です。
JAX JAPANでは、食品工場で使用できる安全性の高い製品としての証明「NSF H1認証」を取得した各種潤滑油を取り扱っております。
なお、NSF H1認証とJAX製品の詳細を知りたい方は、以下のページもあわせてご確認ください。
適切な油膜を長期間維持できる高品質な潤滑油をお探しなら

適切な油膜を長期間維持できる高品質な潤滑油をお探しならJAXJAPANにお任せください。
JAX JAPANでは、耐熱性や耐水性、安全性に優れた各種潤滑剤を取り揃えています。
自社の用途や環境に適した高品質の潤滑剤をお探しの方は、ぜひJAX製品の使用をご検討ください。
また、自社にとって最適な潤滑油が分からない場合は、専門的な知見によるアドバイスも可能です。
潤滑油に関するお困りごとは、JAX JAPANまでお気軽にご相談ください。
【関連記事】工業用潤滑油の種類・粘度・選び方を徹底解説!最適な潤滑油を見つけよう
【関連記事】潤滑油の摩擦係数とは?上昇で起こる3つのデメリットと対処法を解説