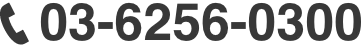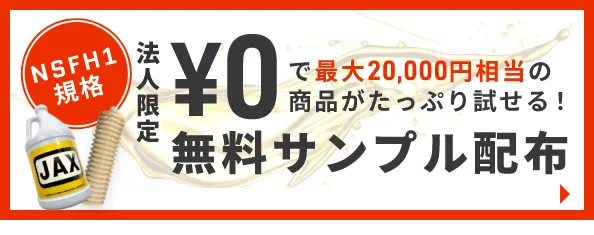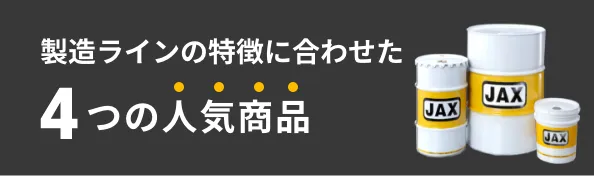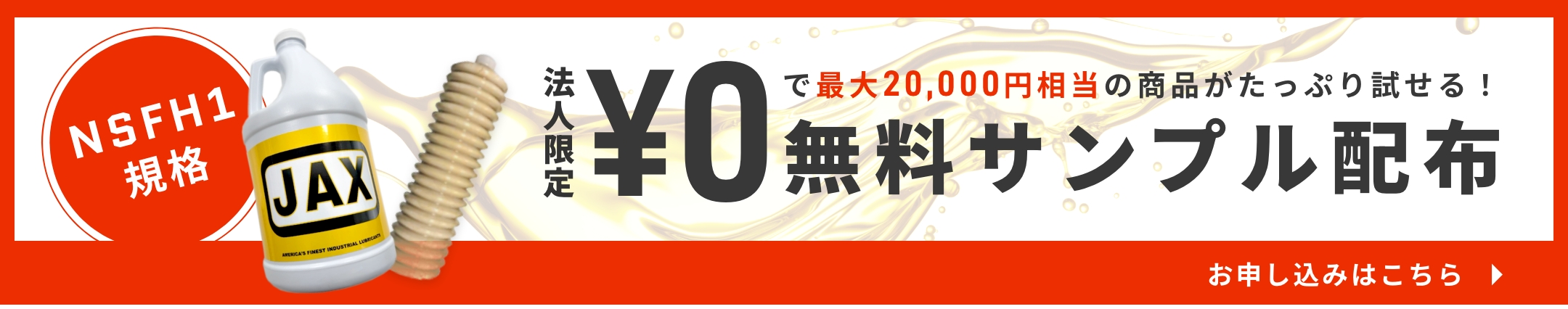グリースの粘度とは?ちょう度との違いや動粘度・粘度指数について解説
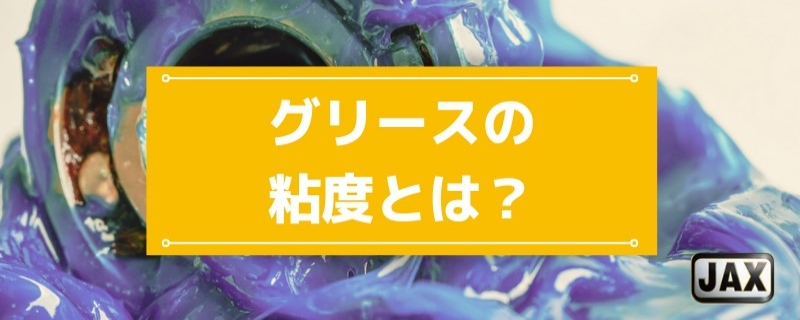
グリースは半固体状であるため、一定の粘度値をもちません。
粘度の代わりに「ちょう度」というグリース特有の指標が用いられます。
粘度やちょう度は、潤滑剤の流動性や抵抗の強さなどを示す重要な指標です。
グリースの粘度・ちょう度を理解することで、機械の寿命や性能を最大限に引き出せるでしょう。
この記事では、グリースの粘度とは何か、ちょう度との違いや粘度が変化する要因についてわかりやすく解説します。
グリースに求められる性能もあわせて紹介するので、ぜひ参考にしてください。
グリースの粘度とは

グリースは非ニュートン流体であるため、せん断応力により粘度が変化する特性があります。
そのため、潤滑油のようなニュートン流体とは異なり、一定ではありません。
通常、力が加わると変形速度に比例して流体に抵抗力が働きます。
しかし、非ニュートン流体の場合は、力が加わったときの変形速度と抵抗力の関係が複雑で、単純に比例関係にはありません。
そのため、グリースのような非ニュートン流体では「見かけ粘度」を使います。
せん断力とずり速度の比で表されるため、同じグリースでも力の加え方によって粘度が異なるという特徴があります。
【関連記事】グリースとは?潤滑油との違いや求められる5つの性能、種類を徹底解説
粘度とちょう度の違い
粘度が液体の流れ具合を示すのに対し、ちょう度はグリースの硬さを表す指標です。
例えば、水のようなサラサラした液体は粘度が低く、ハチミツのようなドロドロした液体は粘度が高いことを意味します。
ただし、グリースは、潤滑油と違って半固体の形状をしているため、粘度だけでは評価できません。
そのため、ちょう度という独自の指標を用いて、硬さを9段階で評価します。
グリースの粘度指数
グリースの粘度指数は、温度による粘度変化の度合いを表す指標です。
粘度指数が高いグリースは、温度が変化しても粘度があまり変化しません。
数値が高いほど温度変化に強く、広い温度範囲で安定した潤滑性を発揮できます。
【関連記事】粘度指数とは?計算方法や粘度指数向上剤のメリット・デメリットを解説
グリースの動粘度
グリースの動粘度とは、おもに基油動粘度を意味します。
そもそも動粘度とは、潤滑油の粘度をその液体の密度で割った値であり、粘度の指標に用いられる物性値のことです。
グリースは基油(ベースオイル)と増ちょう剤、少量の添加剤で構成されています。
基油動粘度が示すのは、グリースに含まれるオイル成分である基油の動粘度です。
なお、基油動粘度は、数値が大きいほど粘度が高い傾向にあります。原則として、基油動粘度が小さいグリースは高速回転用として使用し、数値の大きいグリースは低速回転用として使われます。
【関連記事】潤滑油の粘度とは?動粘度と粘度指数についても解説
グリースの粘度(ちょう度)別分類

グリースの粘度(ちょう度)は、以下の2つの規格で分類されています。
- NLGI(米国潤滑グリース協会)
- JIS(日本工業規格)
ここからは、各規格の分類について詳しく解説します。
ちょう度番号による分類
ちょう度番号とは、グリースの粘度(ちょう度)を表す規格であり、数値が大きいほど硬さが増していきます。
なお、ちょう度番号は、おもにNLGLグレードとJIS分類の2つの規格で表記されるケースが一般的です。
NLGI(アメリカ潤滑グリース協会)が定めたNLGLグレードを日本国内でも適用しているため、実質的な内容は変わりませんが、単位の表記は異なります。
グリースのちょう度とちょう度番号の関係性は、以下の通りです。
| ちょう度(25℃) | ちょう度番号 (JIS分類) |
ちょう度番号 (NLGLグレード) |
グリースの硬さ |
| 445~475 | 000号 | No.000 | 流動状 |
| 400〜430 | 00号 | No.00 | 半流動状 |
| 355~385 | 0号 | No.0 | 極めて柔らかい |
| 310~340 | 1号 | No.1 | やや柔らかい |
| 265~295 | 2号 | No.2 | 標準的な硬さ |
| 220~250 | 3号 | No.3 | やや硬い |
| 175~205 | 4号 | No.4 | 硬い |
| 130~160 | 5号 | No.5 | 極めて硬い |
| 85~115 | 6号 | No.6 | 極めて硬い |
ちょう度の数値は大きいほど、柔らかい性質を示すのに対して、ちょう度番号による分類では数字が小さいほど、柔らかいグリースとなります。
なお、すべり軸受けにおいてグリース潤滑を行う場合、ちょう度番号1のグリースを基準にし、回転速度や使用温度に応じてちょう度を調整します。
回転速度が大きい、または使用温度が低い場合は、1ランク柔らかいグリースを選択すると良いでしょう。
グリースの粘度(ちょう度)が変化する要因

グリースの粘土(ちょう度)が変化する要因は、以下の2つです。
- 温度
- せん断力
潤滑剤は使用環境によって大きく変化する特性を持っているため、要因を考慮したうえで自社機械に適した製品を選定しましょう。
要因①:温度
グリースの粘度は、温度の影響を受けて大きく変動します。
一般的に、温度が上がるとグリースの粘度は低下し、流動性が高くなります。
一方、温度が下がると粘度が上昇し、グリースは硬くなるのです。
通常のリチウム石けんを増ちょう剤とするグリースでは、約130°Cが半固体状態を維持できる限界温度です。
また、一般的なグリースは−20°C付近で基油の流動性が失われやすくなります。
低温環境では、粘度が上昇して硬くなるため、低温安定性や流動点に優れた化学合成油をベースとしたグリースが適しているでしょう。
使用用途に適した高い耐熱性を誇るグリースをお探しの方は、下記の「耐熱商品ラインナップ」をご確認ください。
要因②:せん断力
グリースに外部からせん断力が加わると、流動性が高まり、粘度が低下します。
具体的には、グリースに含まれる増ちょう剤が細い繊維状の構造を持ち、網目状の構造が油を包み込むことで、半固体状態を保っているためです。
しかし、外部からせん断力が加わると、繊維構造が破壊され、流動性が高まります。
せん断力が止まると、繊維構造が元に戻ることで、半固体状態になり粘度が回復します。
このように、グリースはせん断力によって粘度が可逆的に変化する特性を持っているのです。
そのため、せん断力が強いほど液状化し、潤滑性能が低下する可能性が高まるでしょう。
グリースに求められるおもな性能

グリースに求められる性能は、以下の5つです。
- 適性ちょう度
- 機械的安定性
- 酸化安定性
- 高温・低温耐性
- その他の特性
各性能を詳しく解説するので、グリースを選定する際の参考としてご活用ください。
性能①:適性ちょう度
グリースの適性ちょう度は、潤滑性能に大きな影響を与える重要な指標です。
以下のようにちょう度が合っていないと、機械の動きがスムーズでなくなる可能性が高まります。
- 柔らかすぎる:機械部品から漏れやすく、油膜切れが起こりやすくなる
- 硬すぎる:動作時に強い抵抗がかかり、潤滑が不十分になる
なお、ちょう度は00から6までの9段階で表されており、一般的にちょう度番号1,2が広く使用されています。
使用条件に合わせて、適切なちょう度を選ぶことで、機械性能を最適化し、スムーズな動作を維持できるでしょう。
【関連記事】グリースのちょう度とは?ちょう度番号の違いや選定の目安を解説
性能②:機械的安定性
グリースには、機械的な力に対する耐性である機械的安定性が欠かせません。
なぜなら、機械的な力であるせん断力が加わることで、以下の問題が起こる可能性があるからです。
- グリースの漏れ
- 機械動作の不具合
- 騒音の発生
なお、求められる性能は、機械の回転速度や荷重条件によって異なります。
機械の寿命を延ばし、メンテナンスの手間を減らすためにも、機械安定性の高いグリースを選びましょう。
性能③:酸化安定性
グリースを使用する機械部品は、高温や空気に晒されることが多いため、酸化安定性が必要です。
酸化安定性とは、グリースが高温時などに空気中の酸素と反応して劣化する酸化現象を防ぐ性能です。
例えば、食品加工機械のベアリングやモーター部分に使用されるグリースが高温や酸素に触れると、酸化が進行します。
酸化によって、グリースの潤滑性能が低下し、機械の動作がスムーズでなくなる可能性があります。
なかでも食品工場では、酸化によって劣化したグリースが食品に混入するケースも少なくありません。
食品の安全性に関わる問題を防ぐためにも、特に、食品工場で使用されるグリースには酸化防止剤が含まれている傾向があります。
性能④:高温・低温耐性
機械部品は、周囲の熱や摩擦熱の影響で高温になったり、寒冷な環境で低温になったりする場合があります。
そのため、グリースには高温や低温に耐えられる性能が必要です。
例えば、冷凍食品工場では、機械が低温環境にさらされるため、グリースが冷えて硬くなると、機械の動きが鈍くなります。
ベアリングなどの潤滑部分に硬化したグリースが詰まると、機械の起動時にトルクが増え、余分なエネルギーを消費したり、部品に過度の負担をかけたりしてしまう可能性があります。
一方、高温下で稼働する機器では、グリースの中に含まれる増ちょう剤が分解され、液状化してしまうケースもあるでしょう。
なお、一般的なグリースの使用可能温度は、約-10〜60℃です。
使用可能温度の範囲内であれば、潤滑性能を維持し続けられるでしょう。
JAX JAPANが提供する「ハローガードFG」は滴点が254〜316°Cと高く、熱や水、高負荷、衝撃荷重から機器を保護する万能グリースです。
食品機械用途に最適な性能を備えたグリースをお探しの方は、ぜひ導入をご検討ください。
ハローガードFGを導入したお客様の声
実際にハローガードFGを導入したお客様は、以下のような効果を実感しています。
◾️食品工場のメンテナンス担当者
JAX ハローガード FG2 を使用するようになってから、機械の動作がスムーズになり、異音も減少しました。食品機械に適した NSF H1認証グリースなので、安心して使用できます。
◾️製菓メーカーの設備管理者
これまで使用していたグリースは、高温環境での耐久性に不安がありましたが、JAX ハローガード FG2 は高温でもしっかりと潤滑性能を維持してくれます。機械のメンテナンス回数が減り、生産効率も向上しました。
◾️飲料工場の技術責任者
食品安全規格をクリアしながらも、優れた耐摩耗性を持つグリースを探していました。JAX ハローガード FG2 はその両方を満たしてくれた上、長期間の使用でも劣化が少なく、コストパフォーマンスも良好です。
◾️食品包装機械メーカーのエンジニア
お客様からの要望で食品グレードのグリースを採用する必要がありました。JAX ハローガード FG2 はNSF H1認証で安心感があり、さらに機械の耐久性向上にも貢献しています。
上記の声と類似するお悩みを抱えている方は、ハローガードFGの導入をおすすめします。
【関連記事】JAXのH1グリース「ハローガードFG」ってどんな製品?
性能⑤:その他の特性
グリースには使用環境や用途に応じて、以下の特性が求められる場合もあります。
- 防錆・腐食防止性
- 耐水性
- 極圧性
- 低トルク耐性
- 耐摩耗性 など
例えば、水を使用する環境では、金属の錆や腐食が問題となるため、グリースには優れた防錆性と腐食防止性が求められます。
グリースを選ぶ際は、以下の要素を総合的に考慮することが大切です。
- 使用環境
- 機械特性
- グリース自体の特性 など
使用条件に最適なグリースを選ぶことで、機械性能を長期間にわたって維持できるでしょう。
なお、JAX JAPANのH1グリースは、偶発的な食品接触が発生する可能性のある環境で使用できる安全性の高い製品です。
同時に優れた機械的安定性と耐荷重性能を備え、過酷な環境でも機械部品の摩耗や劣化を抑える効果を発揮します。
自社製品の安全性と機械寿命の長期化を見込める高品質なグリースをお探しの方は、ぜひ導入をご検討ください。
グリースの粘度に関するよくある質問
ここからは、グリースの粘度に関するよくある質問とその回答を紹介します。
Q.1 高粘度グリースの特徴やおもな用途を教えてください
粘度(ちょう度)の高いグリースには、以下のような特徴があります。
- 耐熱、耐水、耐酸性に優れる
- 潤滑面へ付着性に優れ、金属の摩耗・焼き付きを防ぐ効果が高い
- 滑り面で発生する異常音を抑制する
- 厚い被膜を形成できるため防錆・耐腐食性も高い など
このような特徴から高粘度グリースは、おもに以下のような用途で活用されています。
- 各種工業・産業機械の軸受けや摺動面などの潤滑
- 高速・高温・高荷重の各種軸受け部、減速機の潤滑
- 水分が混入・接触する各種機械部品の潤滑および防錆剤として
- 機械動作の騒音対策として など
原則として、負荷がかかりやすいハードな環境ほど、高粘度のグリースが適しているといえるでしょう。
Q.2 低粘度グリースの特徴やおもな用途を教えてください
粘度(ちょう度)の低いグリースは、以下のような特徴を備えています。
- 粘性抵抗が低く、安定した回転トルクが得られる
- 高速回転時でも発熱しにくい
- 広い温度範囲で良好な潤滑性を保てる
- 酸化安定性に優れる
- 水分の侵入による軟化や極圧性の低下が発生しにくい など
なお、低粘度グリースのおもな用途としては、高速回転する摺動部などが挙げられます。
また、粘性抵抗が低く、動力が伝わりやすいことから、運転効率が下がる寒冷地や冬季の機械潤滑にも適しています。
Q.3 グリースの粘度はどのように測定しますか?
グリースの粘度(ちょう度)は、以下のように測定します。
- 試料の温度を25℃に保つ
- 規定の混和器を使って、60回往復混和(せん断)する
- 円錐型の専用器具を垂直を保ちながら試料中に沈める
- 5.0±0.1秒間進入させた後、器具が沈んだ深さを測定する
- 深さの値を10倍した数値がちょう度となる
専用器具が深く沈む=試料は柔らかいことになるため、ちょう度の数値が大きいほど流動性の高いグリースといえます。
自社の潤滑環境に適した粘度のグリースをお探しなら

自社の潤滑環境に適した粘度のグリースをお探しの方は、JAX JAPANが提供する「H1グリース」をぜひご検討ください。
H1グリースは、NSF H1規格を取得した食品機械用グリースであり、国際的にその安全性が認められた潤滑剤です。
優れた機械的安定性と耐荷重性能を持ち、過酷な環境でも機械部品の摩耗や劣化を抑える効果があります。
無料サンプルもご用意していますので、興味のある方はお気軽にJAX JAPANまでお問い合せください。
また、JAXJAPANでは、グリース以外にもさまざまな用途や環境に対応した高性能な潤滑剤を多数取り扱っています。
自社に最適な潤滑剤をお探しの方は、以下の「商品ラインナップ」をご確認ください。
【関連記事】耐熱グリスとは?成分別におもな種類と特徴、使用可能温度を解説
【関連記事】食品機械用グリスとは?一般的な製品との違いやH1規格について解説